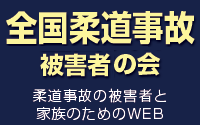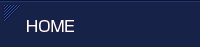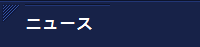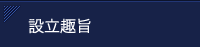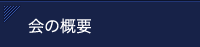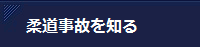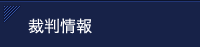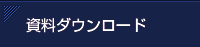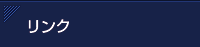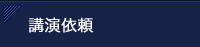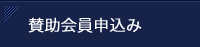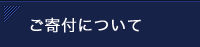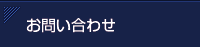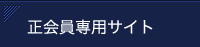脊髄損傷
脳損傷は初心者が多く受傷しているが、脊髄損傷の多くは柔道経験者である。
脳損傷事故は乱取り中に多く受傷しているのに対し、脊髄損傷は試合中に受傷しているケースが多い。
参考資料の「柔道試合・練習中の脳・脊髄損傷への対応指針(全柔連)」にも記載してあるとおり、頚部の過度の伸展や屈曲により頚髄が損傷される。時には頚椎に脱臼や骨折が起こることもある。手足の動きが悪い、感覚がない、しびれ、痛みなどがある場合は、即救急車を要請し、救急車が到着するまで絶対に動かしてはならない。どうしても動かさなければならない事情がある場合は、畳ごと抱え上げて、けっして揺らさないようにして移動させる。柔道着を掴んで柔道場の隅や通路まで引きずる行為は、取り返しのつかない結果を招く。
事故事例
- 県大会予選で対戦相手が背負い投げを掛けたが技が決まらず、腹ばいで逃げようとする女子生徒の右手袖を相手選手は立ったまま左手で引き、右手でズボンの膝の裏側をつかみ逆立ちにして持ち上げ、頭が畳についた状態でひっくりかえそうとした。途中で被害者の体を持ち上げきれず、回し切れなかった相手は体ごと被害者の上に覆いかぶさって倒れた。
対戦相手の体重も含め140kg以上が被害者の首にかかってC5・6の頸髄損傷で両全手指機能全廃、両下肢機能全廃、体幹機能障害(坐位不能) を負い、身体障害者手帳1種1級となった(高校3年女子)。 - 体育授業の柔道で、身長差15cm、体重差15kgもある生徒との試合で頸髄損傷。親への連絡までに2時間もかかり、電話で母親にどうするか聞き、母親の要請で初めて救急車を呼んだ。
幸い車椅子生活にはならなかったが、右腕の痺れと頭痛が残り、医師からは運動制限と首への負担は厳禁と言われている(高校1年男子)。
【参考資料】
- 柔道試合・練習中の脳・脊髄損傷への対応指針(全柔連)
- 「柔道の安全指導」(全柔連)
- 「柔道選手における頚部外傷の受傷機転から予防を考える p.7(全柔連)
- 「体育活動における 頭頚部外傷事故防止の留意点」(日本スポーツ振興センター)
- 「最悪の事態になり得た危機から、西岡剛選手を救った阪神タイガースのトレーナー」(Yahoo!個人ニュース 土井麻由美筆)