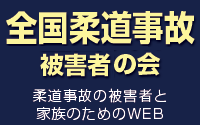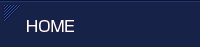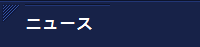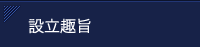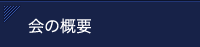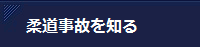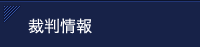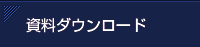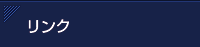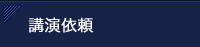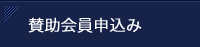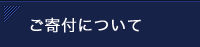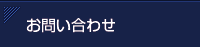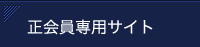昨日の信濃毎日新聞に以下の記事が掲載されました。
全柔連が、安全指導の手引きを改訂し、その中に加速損傷の内容を盛り込むこと、また安全指導講習会への参加を指導者に義務付けるというものです。
| 柔道指導者 講習義務化へ 全柔連が安全指導へ冊子改定
全日本柔道連盟(全柔連、東京)は、柔道による子どもの重大事故が相次いでいることから、安全指導用の小冊子を本年度内に改定する。全柔連が講師を派遣、小冊子を教材に開いている安全指導講習会への参加も指導者に義務付ける方針だ。
学校での事故に詳しい愛知教育大の内田良講師によると、1983(昭和58)年4月から今年6月1日までに中学、高校の柔道部の活動や柔道の授業で110人が死亡している。死因の最多は急性硬膜下血腫で46人。脳と硬膜内の静脈とを結ぶ橋静脈が、急激な外力で引っ張られて切れたとみられる。
松本市の柔道教室では2008年5月、当時小学6年生の沢田武蔵君(14)=松本市=が練習中に男性指導者(37)に投げられた後、意識不明の重体になった。武蔵君は急性硬膜下血腫と診断され、一命を取り留めたが、重い障害を負った。松本署は今月、業務上過失傷害の疑いで指導者の書類を地検松本支部へ送っている。
相次ぐ事故を重く見た全柔連は6月下旬、柔道家や医師、弁護士ら約20人でつくる「安全指導プロジェクト特別委員会」を設置。事故を防ぐ指導法を研究し、小冊子「柔道の安全指導」を改定、安全な指導法を紹介するDVDも作ることにした。
特別委員会の委員で、事故の事例分析をした徳島大学病院の永広信治・脳神経外科長(58)は「中学1年、高校1年の初心者に事故が多い。受け身を十分に習得させ、初心者と熟練者を分けた練習計画を作る必要がある」と指摘する。改定する小冊子には、習熟度に応じた段階的指導や、頭を直接床などにぶつけなくても急性硬膜下血腫が起こることなどを盛り込む見通し。
文部科学省は7月、日本中学校体育連盟(中体連)や国公私立の高校、大学などに対し、全柔連の小冊子を参考に安全指導を徹底するよう求める通知を出している。
信濃毎日新聞 2010年9月21日
|
この国の柔道が、事故の実態を調査せず、事故を放置してきた事を考えれば、この記事の内容には隔世の感があります。
手前味噌ではありますが、今回の決定については全国柔道事故被害者の会の活動が背景にあることは間違いありません。
それまで全柔連が認識さえしていなかった柔道における加速損傷の危険性について言及し、欧米の事故事例を調査し、さらに指導者への安全指導の義務化を唱えてきたのは、私達被害者の会です。
この動きが単なるポーズではなく、本当の安全指導へと繋がる事を願ってやみません。
↑ ページの先頭に戻る