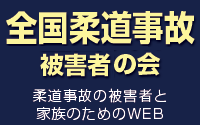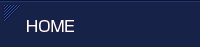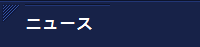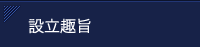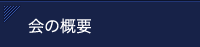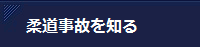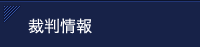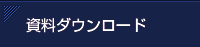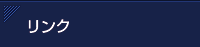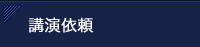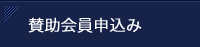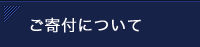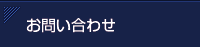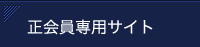柔道指導者の資格制度について – ニュース記事より
昨日お知らせした全柔連の指導者資格制度について報道された記事をご紹介いたします。
(太字部分は当会にて)
■時事通信
「指導者資格制度2年後導入=安全管理徹底へ?全柔連」
全日本柔道連盟は22日に開いた評議員会で、指導者の資質向上や安全管理の徹底を図るため、「指導者資格付与制度」を2013年度から導入することを承認した。
新制度では、資格を指導レベルなどに応じて最高のAからCまで3段階に区分。取得には講習会の受講と審査試験を義務付け、取得後も2?4年の有効期限を設け更新制にする。各都道府県大会で監督が務められるCランクでも三段以上の段位が必要。ただし、学校の部活動で顧問をする教員に対しては例外措置も講じる予定。
初段以上の指導者を対象にした現行の登録制度では、約3万人が登録。しかし、練習や試合中に選手が頭部などを負傷し、最悪死亡に至る事故が相次ぎ、制度の改善が急務になっていた。(2011/04/22-19:52)
■産經新聞
「全柔連が指導者ライセンス制度導入へ」
全日本柔道連盟(全柔連)は22日、東京・講道館で理事会と評議員会を開き、指導者の資質向上を図るため、2013年4月から「指導者資格付与制度」を導入し、3段階のレベルに分けたライセンスを交付することを決めた。
全柔連は全国各地の試合や練習で起きている死亡事故など、指導者の責任が問われる事例が少なくないことを憂慮。小野沢弘史専務理事は「指導者の地位を保証することで社会的信用が高まり、リスク管理にもつながる」と説明した。
これまで20歳以上の有段者であれば指導者登録ができたが、新制度は資格レベルを3段階に分けた。全柔連主催の全国大会で監督ができる「A」は24歳以上で5段以上、地区大会レベルの「B」は22歳以上で4段以上、都道府県大会レベルの「C」は20歳以上で3段以上となっている。
来年までは移行期間で、資格取得希望者は今年6月から来年9月末までに全国で実施される講習会を受講後、全柔連の審査を受ける。
(2011.4.22 20:08)
この資格制度の詳細までは解りませんが、記事を読んで気になった部分を太字にいたしました。
講習会と審査試験を義務付け、資格は永久的なものではなく2年?4年での更新制にするという事ですが、資格制度の導入とその資格が永久的なものではなく更新制になったことは私達の会が提唱をしていた事と同じですので、評価のできる部分であろうと思います。
ただ何より重要なのは、この講習会でどのような講習をされるのか、審査試験なるものがどのような内容と方法でされるのか、だと思います。
過去の事故事例を分析し、統計的数字に基づいた安全講習、事故防止の具体的方法のための講習が必要ですし、また、当然でありますが、医学的知識、運動生理学に基づいた知識を得るための講習も必要になります。
これらの医学、運動生理学を含めた安全への全般的な知識が審査対象にならなければなりません。審査試験が単なる実技試験になっては意味がありません。
この講習会と審査試験の内容については、解り次第詳細をお知らせしたいと思います。
次に時事通信社の報道によると、学校の部活動で顧問をする教員に対しては例外措置も講じる予定だとあります。
当会で繰り返し警鐘をならしている柔道による死亡事故、障害事故の発生件数が最も多いのは学校活動での柔道です。
年間で4人以上の死亡者、年間で10人以上の障害者を出している学校での柔道事故の実態を考えれば、この学校での部活動の顧問の例外措置というのが、どのようなものなるのかが非常に気になります。
この例外措置というものが、安全を犠牲にした例外措置になってはいけません。
例えば、3段以上の有段者の確保ができない学校は例外的に初段でも部活動に限り指導を認めるなどの実技面での例外措置ならまだしも、上述のような安全のための講習会の参加義務や審査試験を免除、あるいは軽減するような内容の例外措置であれば、断固として反対いたします。
ライセンスはA、B、Cの3段階が有り、それぞれで取得段位が違っています。
技等の実技面を指導するためには高段位の方のほうがより高く評価をされているという事でしょうが、高段位の方が優れた指導者であるとは限りません。
何よりも、柔道による事故でこれ以上子どもが犠牲にならない事、まずその事を真摯に考えられる方こそが指導者たる資質を持つ方だと思います。
被害者の会としては、この全柔連の資格制度について、今後もその内容等を注視していきたいと思います。